富士山麓に残された安房の人たちの痕跡は、古文書だけではありません。吉田口の登山道や西麓の人穴などに、33度、66度、108度などと登山した回数を刻んだ個人の記念碑がいくつも建てられています。こうした記念碑を残した人は、先達といって富士講中を率いるリーダーのような立場にあった人たちですが、先達は単に登山の案内をする人ではなく、俗世間にありながら「行名(ぎょうめい)」を持ち、自らさまざまな修練をする宗教者でした。何十回となく登山をくりかえすのも、そうした修練のひとつなのです。
ここでは先達が残した資料をとおして、難行苦行をこなし、また独特の神秘的な世界を持つ、宗教者としての先達の姿とその役割を見てみましょう。

栄行真山(えいぎょうしんさん)百八度登山大願成就記念碑
(山梨県富士吉田市・中の茶屋)
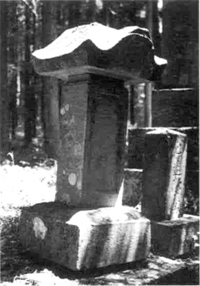
誠行重山(せいぎょうじゅうざん)記念碑
(静岡県富士宮市・人穴(ひとあな))

人穴(ひとあな)の洞穴入口
(静岡県富士宮市)

善行瀧我修行記念碑
(館山市西長田)
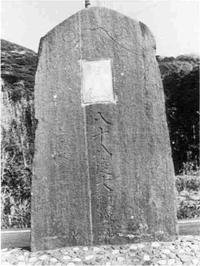
伊行寶海(いぎょうほうかい)八十八度登山記念碑
(館山市洲崎)